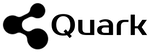以前の記事で、ARグラスのシナリオプランニングを紹介しました。この記事では、ニュース記事を起点に、AIが自動で課題設定をしていますが、本来は人や組織の明確な問題意識から出発すべきです。そこで今回は、課題設定のプロセスだけを切り出し、AIとの議論から自社の課題設定を導くプロセスをご紹介します。
入力情報(ニュース記事と背景知識)は前回と同じですが、自社の立場をやや詳しく入力しています。前回は「国内デバイスメーカーの技術部門」でしたが、今回は国内光学機器メーカーの技術部門とし、保有技術をいくつか入力して実施しました。自社の詳しい状況を課題設定に反映させることを狙い、このあたりの情報を加えました。
同じARグラスというテーマでも、様々な課題設定が想定できることがわかります。以下、条件入力後のAIとの数回のやり取りです。
目次
Q1: 100文字以内の疑問形で課題設定して下さい。
課題設定(日本国内光学機器メーカーの技術部門、2030年想定)
ARグラス市場における競争力維持・強化
- ARグラスの高画質化と低消費電力化は両立可能か? (光学設計、材料、駆動方式の最適化)
- 競合他社がスマートグラスの小型・軽量化を進める中、自社の差別化戦略は何か? (独自技術、ニッチ市場、デザイン)
- ARグラスの普及には、どのようなキラーアプリケーションが必要か? (エンタメ、産業用途、教育、医療)
- ARグラスのUI/UXは、どのような進化を遂げるべきか? (音声操作、ジェスチャー操作、視線追跡)
- ARグラスのデータセキュリティは、どのように確保すべきか? (生体認証、暗号化、プライバシー保護)
- ARグラスの長時間使用における疲労軽減策は? (視覚、脳波、生体計測評価技術の応用)
技術ポートフォリオ戦略
- ARグラス以外の要素技術の応用先は? (医療機器、製造装置、コンポーネント機器)
- ARグラス向け技術開発で培った知見を、既存事業にどう活かすか? (カメラ、プリンター、プロジェクター)
- 注力すべきARグラス関連の要素技術は何か? (光学系、映像認識、UI、通信、セキュリティ、省エネ)
- ARグラス市場の技術トレンドを予測し、研究開発の優先順位をどうつけるか? (市場調査、技術ロードマップ、外部連携)
- ARグラスの要素技術の内製化と外部調達のバランスをどう取るか? (コスト、技術力、サプライチェーン)
- 環境配慮技術をARグラス開発にどう組み込むか? (バイオマスプラスチック、リサイクル設計、省エネ)
生産体制・サプライチェーン戦略
- ARグラス量産体制構築のボトルネックは何か? (製造装置、品質管理、人材育成)
- ARグラスのサプライチェーンにおけるリスクは何か? (部品調達、地政学、災害)
- ARグラスの製造コストを削減するにはどうすべきか? (自動化、内製化、サプライヤー交渉)
- ARグラスの品質を安定させるにはどうすべきか? (検査体制、品質管理システム、サプライヤー監査)
- ARグラスの生産拠点をどこに置くべきか? (コスト、リスク、市場アクセス)
- ARグラスの製造における環境負荷を低減するには? (省エネ、省資源、廃棄物削減)
外部連携戦略
- ARグラス開発で協業すべき企業は? (デバイスメーカー、ソフトウェア会社、コンテンツプロバイダー)
- ARグラス関連の技術を持つスタートアップへの投資戦略は? (投資目的、投資規模、投資時期)
- 大学・研究機関との共同研究テーマは? (基礎研究、応用研究、人材育成)
- 業界団体・標準化団体への参加意義は? (情報収集、技術標準、ロビー活動)
- オープンイノベーションを推進するにはどうすべきか? (アイデア募集、技術交流、共同開発)
- 海外企業との連携におけるリスクは? (技術流出、知的財産、文化摩擦)
Q2: 技術的な切り口の優先度を上げて下さい。
課題設定(日本国内光学機器メーカーの技術部門、2030年想定)
ARグラスの光学部材・技術における技術的優位性確立・維持
- 微小光学素子(マイクロレンズアレイ、回折格子等)の設計・製造技術で、競合他社に対しどのような差別化を図るべきか?(高精度、小型化、高効率、量産性)
- 自由曲面レンズ、回折光学素子、メタレンズ等の要素技術を組み合わせ、ARグラス全体の小型・軽量化、高画質化にどう貢献できるか?(光学設計、製造技術、評価技術)
- ARグラスの光導波路における光損失を最小化し、効率的な光利用を実現するには、どのような材料・構造・製造プロセスが最適か?(材料開発、微細構造形成、プロセス制御)
- ARグラスの視野角拡大と収差補正を両立させるための革新的な光学設計は? (自由曲面、回折光学素子、メタレンズの組み合わせ)
- 屋外での視認性向上のため、高輝度マイクロディスプレイと高効率光学系の組み合わせで、どの程度まで消費電力を抑えられるか? (マイクロディスプレイ技術、光学設計、省エネ技術)
- 人間の視覚特性(両眼視差、輻輳、調節)を考慮した、より自然で快適なAR体験を提供する光学設計とは? (視覚生理学、ヒューマンファクター、光学設計)
既存技術のARグラスへの応用・展開
- カメラレンズで培ったコーティング技術、研磨技術、評価技術を、ARグラスの光学系にどう応用し、性能向上に繋げるか?(光学薄膜、表面処理、品質管理)
- 映像認識技術をARグラスに搭載し、どのような新しいユーザー体験を提供できるか?(SLAM、物体認識、ジェスチャー認識)
- カラーマネジメントシステムをARグラスに適用し、現実世界との自然な色再現を両立するには?(色空間変換、キャリブレーション、環境光適応)
- 超音波モーター、エンコーダー等の精密制御技術をARグラスに活用し、どのような新しい機能や価値を提供できるか?(視線追跡、焦点調整、手振れ補正)
- 環境配慮技術(バイオマスプラスチック等)をARグラスの材料に活用する際の課題と解決策は?(材料強度、耐久性、光学特性、環境負荷)
- 医療機器開発で培った人間・生理計測評価技術をARグラスに応用し、長時間の快適な使用をサポートするには?(脳波計測、視線計測、疲労評価、UXデザイン)
新規技術領域への挑戦
- メタマテリアル、フォトニック結晶等の革新的な光学材料・素子をARグラスに活用する可能性は?(基礎研究、応用研究、デバイス開発)
- AI・機械学習を活用し、ARグラスの光学設計・製造プロセスを最適化するには?(自動設計、シミュレーション、品質予測)
- 量子ドット、有機EL等の新しい発光材料をARグラスの光源として活用する際の課題と解決策は?(高効率、高色純度、長寿命、低コスト)
- ホログラフィー、ライトフィールド等の新しい映像表示技術をARグラスに適用する可能性は?(3D表示、自然な焦点深度、視覚疲労軽減)
- ARグラスと脳波インターフェースを組み合わせ、どのような新しいアプリケーションや価値を提供できるか?(ブレイン・マシン・インターフェース、ニューロテクノロジー、医療、エンタメ)
- ARグラスのバッテリー消費を劇的に削減する革新的な省エネルギー技術は? (エネルギーハーベスティング、低消費電力回路、最適化アルゴリズム)
Q3: どれか一つを選択する場合のポイントは?
戦略検討フローで検討する課題の選択に関するアドバイスです。
選択のポイント
- 自社の強みとの整合性: X社が持つ要素技術、特に光学コンポーネント、カラーマネジメントシステム、映像認識技術、超音波モーター、エンコーダーなどの強みを最大限に活かせる課題を選ぶべきです。
- 市場の成長性と競争環境: ARグラス市場は成長が見込まれますが、競争も激化しています。Xrealのような新興勢力の台頭や、Appleのような巨大企業の参入を踏まえ、自社の技術で差別化できる領域を見極める必要があります。
- 技術的な実現可能性: 短期的な実現可能性と、長期的な成長を見据えた要素技術の獲得、という2つの視点を持つことが重要です。
- リスクと機会のバランス: あまりにもリスクの高い課題は避けるべきですが、同時に、現状維持に甘んじることなく、新たな市場機会を創出できる可能性のある課題を選ぶべきです。
- シナリオプランニングの適合性: シナリオプランニングは、不確実性の高い将来を想定し、複数のシナリオに基づいて戦略を検討する手法です。そのため、複数のシナリオが考えられる課題を選ぶことが重要です。
おすすめの課題
上記のポイントを踏まえ、今回は以下の課題を選択することを推奨します。
「ARグラスの光学部材・技術における技術的優位性確立・維持」
この課題は、X社の強みである光学技術を最大限に活かせるだけでなく、市場の成長性と競争環境、技術的な実現可能性、リスクと機会のバランス、シナリオプランニングの適合性のすべての面で優れていると考えられます。
選択理由
- 強み: X社は長年培ってきた光学技術をARグラスに応用することで、他社に対する優位性を確立できます。
- 市場: ARグラスの性能を左右する光学部材・技術は、競争優位性の源泉となります。
- 実現可能性: 既存の技術を応用しつつ、新規技術の開発にも取り組むことで、短期的な成果と長期的な成長の両立が可能です。
- リスクと機会: 技術革新のスピードが速いARグラス市場において、光学部材・技術での優位性を確立することは、リスクを軽減しつつ、大きな市場機会を獲得することにつながります。
- シナリオプランニング: 光学系の小型化、高画質化、低消費電力化など、複数の技術的な方向性が考えられるため、シナリオプランニングに適しています。
シナリオプランニングの方向性
選択した課題についてシナリオプランニングを行う場合、以下のような方向性が考えられます。
- 技術トレンド: 光学系の小型化、高画質化、低消費電力化、自由曲面、回折光学素子、メタレンズなどの技術トレンドを考慮します。
- 競合の動向: Xreal、Apple、Metaなどの競合他社の技術戦略や製品戦略を分析します。
- 市場のニーズ: ARグラスの用途(エンターテインメント、ビジネス、教育、医療など)に応じた光学性能のニーズを把握します。
- 規制の変化: ARグラスの安全性やプライバシーに関する規制の変化を予測します。
これらの要素を組み合わせ、複数のシナリオを作成し、それぞれのシナリオにおけるX社の最適な戦略を検討することで、より強固な技術開発戦略を策定することができます。
Q4: 具体的に何が推奨されますか?
上記の情報とこれまでの議論を踏まえ、「ARグラスの光学部材・技術における技術的優位性確立・維持」のうち、1番を推奨します。
1. 微小光学素子(マイクロレンズアレイ、回折格子等)の設計・製造技術で、競合他社に対しどのような差別化を図るべきか?(高精度、小型化、高効率、量産性)
推奨理由
- 強みとの整合性: X社は、カメラレンズをはじめとする光学製品で培ってきた微細加工技術、精密成形技術、光学設計技術において高い競争力を持っています。これらの技術をマイクロレンズアレイや回折格子といったARグラス向け微小光学素子に展開することで、技術的な優位性を確立できる可能性が高いと考えられます。特に、モールド技術(高精度の非球面レンズ、DOレンズの金型製造技術)は、マイクロレンズアレイの量産に大きく貢献できると考えられます。
- 市場のニーズ: ARグラスの小型化・軽量化、高画質化、低消費電力化を実現するためには、高性能な微小光学素子が不可欠です。特に、高屈折率材料、異方性材料などの新規材料を用いた素子や、自由曲面形状、回折構造などの複雑な形状を持つ素子の開発は、ARグラスの性能向上に大きく貢献すると期待されます。
- 競争環境: Xrealなどの新興勢力が低価格帯のARグラスで市場を拡大する中、X社は高画質・高機能なARグラス向けに、高性能な微小光学素子を提供することで差別化を図ることができます。
- 将来の意思決定:
- 2030年、Xrealが超高解像度・低消費電力のメタレンズアレイを搭載したARグラスを発表。X社は、自社の回折格子技術を基盤とした、より高性能な導波路型ARグラス用光学系の開発を継続すべきか?
- 2030年、ARグラス市場がコンシューマー向けから産業用途へシフト。X社は、特定の産業分野(医療、製造など)に特化した、高耐久性・高信頼性の微小光学素子の開発に注力すべきか?
- 2030年、中国メーカーが低コストなARグラス用微小光学素子の量産体制を確立。X社は、高付加価値なARグラス用光学系モジュール(マイクロレンズアレイ+導波路など)の開発にシフトすべきか?
シナリオプランニングのポイント
この課題についてシナリオプランニングを行う場合、以下のような要素を考慮する必要があります。
- 技術トレンド: メタレンズ、自由曲面レンズ、回折光学素子、量子ドットなどの要素技術の進化を予測します。
- 材料開発: 高屈折率材料、低分散材料、高透明性材料などの新規材料の開発動向を把握します。
- 製造技術: 微細加工技術、精密成形技術、薄膜形成技術などの製造技術の進歩を予測します。
- 市場のニーズ: ARグラスの用途(エンターテインメント、ビジネス、教育、医療など)に応じた光学性能のニーズを把握します。
- 競合の動向: HOYA、ニコン、コーニングなどの競合他社の技術戦略や製品戦略を分析します。
これらの要素を組み合わせ、複数のシナリオを作成し、それぞれのシナリオにおけるX社の最適な戦略を検討することで、より強固な技術開発戦略を策定することができます。
ひとこと
AIによる自動の課題設定では、バリエーションに限界があることがわかっています。LLMのパラメータを調整しても、やはり限界がありました。シナリオプランニングにとっての課題設定は、その後の内容を大きく左右し、したがって最終的な結論である戦略にも大きく影響します。自社にとっての課題を正しく捉える、その時点ですでに結論は決まっているのかもしれません。そういう意味で、課題設定のプロセスは、理想的には、問題意識を持つ「人」が介入すべきプロセスだと考えます。
シナリオプランニングの自動化は目指すものの、必要に応じて個別にプロセスを切り出し、人間が介入して「意思」を投入できるシステムを考えています。AIが深く入り込んだ先で、誰がやっても同じ戦略が出てしまっては、差がつかなくなってしまいます。AIと人との協調が求められているのだと思います。
クォークでは、生成AIを活用した客観性のある戦略プランニング、特定分野に専門特化した生成AIの構築など、企業のR&Dを情報面でサポートする取り組みを継続しております。全国からのお問い合わせをお待ちしております。