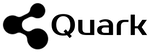企業の研究開発者や開発企画部門にとって、未来の顧客ニーズを鮮明に描き出し、それに応える製品やソフトウェアを開発することは喫緊の課題です。例えば、「5G/6G環境下で、よりリアルなXR体験を実現するための技術的障壁は何か?」「進化し続ける大規模言語モデルを、倫理的に活用した革新的なアプリケーションはどのように生み出せるのか?」といった具体的な問いに対し、明確な答えを見出すことは容易ではありません。
今回あらためて、このような将来の不確実性に対処し、確固たる研究開発戦略を策定するための強力なツール、シナリオプランニングを紹介します。技術革新を軸とした未来の可能性を探り、その洞察を研究開発戦略へと落とし込む道筋を、以下の構成で解説します。
- シナリオプランニングとは
- シナリオプランニングの事例
- シナリオを活かした研究開発戦略の立案
シナリオプランニングとは
シナリオプランニングとは
現代社会は、技術革新の加速、地政学的な変動、環境問題の深刻化など、予測困難な要素に満ち溢れています。企業を取り巻く事業環境も例外ではなく、その複雑性と不確実性は増すばかりです。このような時代において、従来の予測や計画に固執するだけでは、長期的な視点を見失い、変化の波に乗り遅れる危険性があります。そこで注目されるのが、「シナリオプランニング」という意思決定支援ツールです。
シナリオプランニングは、まさにこのような事業環境の不確実性や構造的な変化に正面から向き合い、長期的な視点に立った意思決定を可能にするための手法です。その核心となるのは、現在認識されている重要な不確実性を軸に、組織を取り巻く未来がどのように展開していく可能性があるのかを、複数のストーリーとして描き出すことにあります。これらのストーリー、すなわち「シナリオ」は、単なる未来予測ではありません。現実の世界は、私たちの予測や計画通りに進むとは限らないからです。不確実性の存在を前提とし、起こりうる複数の未来の可能性を視野に入れることこそが、シナリオプランニングの重要な視点となります。
では、なぜ複数のシナリオを検討する必要があるのでしょうか。その目的は、特定の未来を正確に予測することではありません。むしろ、複数の未来の可能性を「リハーサル」することによって、現在行うべき意思決定をより良いものにすることにあります。異なる未来のシナリオを検討することで、私たちはそれぞれのシナリオにおける潜在的なリスクや機会を事前に認識し、それらに対応するための戦略やアクションを準備することができます。これは、あたかも事前に災害避難訓練を行うことで、実際の災害発生時に冷静かつ適切な行動を取れるようにするのに似ています。
シナリオは、現在の事業環境がどのような要因によって、どのような方向へ変化していくのかを理解し、それらの変化に適応するための道筋を示すストーリーです。それは、組織が直面する可能性のある未来の姿を具体的に描き出し、それぞれの未来においてどのような課題が生じ、どのような機会が生まれるのかを考察するプロセスを通じて、現状の戦略や意思決定の脆弱性や強みを浮き彫りにします。
シナリオプランニングは、単に未来を予測するのではなく、未来に対する私たちの「認識」そのものを変革する力を持っています。複数の異なる未来シナリオを検討することで、私たちは既存の思考の枠組みから解放され、より柔軟で多角的な視点を持つことができるようになります。これにより、これまで見過ごしてきたリスクや機会に気づき、より強靭で持続可能な組織を構築するための戦略を練り上げることが可能になるのです。
不確実な事業環境において、長期的な視点を持って舵取りを行うことは、組織の存続と成長にとって不可欠です。シナリオプランニングは、まさにそのような状況下で、私たちに羅針盤を与えてくれる強力なツールと言えるでしょう。未来を「リハーサル」し、現在行うべき最善の意思決定を導き出す。それが、シナリオプランニングの本質的な価値なのです。
シナリオプランニングの歴史
シナリオプランニングの起源は、第二次世界大戦後のアメリカ空軍における戦略的対応プログラムに遡ります。不確実な未来の戦況に対応するための備えとして考案されたこの手法は、その後、1960年代にハーマン・カーンのハドソン研究所やスタンフォード・リサーチ・インスティチュートなどによって、未来予測のツールとして発展しました。
シナリオプランニングが経営戦略の重要な要素として確立されたのは、1970年代以降のロイヤル・ダッチ・シェルによる貢献が大きいと言えます。シェルは、シナリオを単なる未来予測の枠組みとして捉えるのではなく、組織全体が複数の未来の可能性について深く考察し、それに基づいてより良い意思決定を行うための学習プロセスとして活用しました。
シェルのシナリオプランニングの成功事例として特筆されるのは、第一次オイルショック(1973年)や1986年の石油価格暴落といった、予測困難な事態をシナリオを通じて事前に認識し、適切な対応を講じたことです。これにより、競合他社が混乱する中で、シェルは市場における優位性を確立し、1970年には業界最下位であったにもかかわらず、1990年には世界最大の石油会社へと成長を遂げました。
シェルの洞察力は経済分野に留まらず、ゴルバチョフ書記長の登場以前にソ連経済の構造的な問題を指摘し、その崩壊の可能性を示唆するシナリオを作成していました。また、南アフリカにおけるアパルトヘイト(人種隔離政策)の撤廃という歴史的な転換期においても、シェルはシナリオを用いた議論を支援し、社会変革の一翼を担いました。
このように、シナリオプランニングは、当初は軍事戦略のツールとして誕生しましたが、その後、未来予測の手法、企業の経営戦略、さらには社会的な課題解決のための議論の枠組みへと、その応用範囲を大きく広げてきました。不確実性が増す現代社会において、単一の予測に頼るのではなく、複数の未来の可能性を探求し、それに対する備えを組織にもたらすシナリオプランニングは、ますますその重要性を増しています。
シナリオと予測の違い
シナリオは、未来を具体的な物語として描き出す手法であるため、しばしば「予測」と混同されます。しかし、この二つは未来へのアプローチにおいて、根本的に異なる性質を持っています。その最も重要な違いは、未来に内在する「不確実性」をどのように認識し、取り扱うかという点にあります。
従来の「予測」のアプローチは、多くの場合、過去のデータや現在のトレンドを分析し、それらを基に未来を単一の線として描こうとします。例えば、直近の成長トレンドが今後も継続すると仮定したり、過去のパターンが繰り返されると想定したりします。また、時には客観的な根拠に乏しい、例えば「V字回復」のような楽観的な見通しが、予測の根拠となることもあります。
米国のエネルギー省(DOE)が公表している「Energy Outlook」における原油価格の予測の変遷を示す図は、この傾向を如実に物語っています。1980年の第二次オイルショック後や2000年以降の予測値は、当時の急激な価格変動という直近のトレンドをそのまま未来に外挿した形となっています。一方、1980年代後半から90年代にかけての予測には、「現在は価格が下落しているものの、いずれ過去の高水準に戻るだろう」という、過去の経験に基づいた期待感が色濃く反映されています。これらの予測は、過去のデータや直近の動向に偏重するあまり、構造的な変化や突発的な事象といった、本質的な不確実性を十分に考慮しているとは言えません。
これに対して、シナリオプランニングは、未来の事業環境を単一の決定されたものとして捉えるのではなく、複数の、同様に起こりうる可能性がありながらも、構造的に大きく異なる未来の姿を描き出します。このアプローチの根底には、「未来は部分的に予測可能であるものの、その核心には本質的な不確実性が存在する」という認識があります。技術革新の方向性、地政学的なリスク、消費者の価値観の変容、規制の変化など、予測モデルだけでは捉えきれない多くの要因が、未来の事業環境を大きく左右する可能性があるからです。
シナリオプランニングの主眼は、特定の未来を正確に当てることではありません。むしろ、複数の「起こってもおかしくない未来=シナリオ」を多角的に検討し、それぞれのシナリオが現実になった場合に、自社の事業や戦略がどのような影響を受けるのかを事前に深く考察することにあります。これにより、予期せぬ事業環境の変化に「虚を突かれる」リスクを軽減し、どのような未来が到来しても柔軟に対応できる、強靭な意思決定と戦略立案を目指すのです。
つまり、予測が単一の未来像を描き出そうとするのに対し、シナリオは複数の可能性のある未来の「物語」を提示します。予測が「何が起こるか」を特定しようとするのに対し、シナリオは「何が起こりうるか」という幅広い視野を提供します。そして、シナリオプランニングは、これらの複数の未来シナリオを検討することで、現在行うべき意思決定の堅牢性を高め、未来の不確実性に対する組織の適応力を向上させることを目的としているのです。不確実性を真正面から受け止め、多様な未来の可能性を探求する姿勢こそが、シナリオプランニングと従来の予測アプローチとの最も本質的な違いと言えるでしょう。
シナリオプランニングの背後にある考え方
シナリオプランニングは、未来は単一の予測では捉えきれないという認識を基盤としています。事業を取り巻く環境は常に変動し、予期せぬリスクや不確実性に満ち溢れているからです。この前提に立ち、不確実性を真正面から捉え、むしろそれを競争優位の源泉へと転換させるという野心的な考え方が、シナリオプランニングの根底にはあります。
未来を一点で予測することは不可能である以上、単一の将来見通しに基づいて経営戦略を策定することは、極めて危険な行為と言わざるを得ません。しかしながら、企業経営者は、投資をはじめとする将来の業績を左右する重要な決断を、常に現在において下さなければなりません。そこで、複数のシナリオを描き出すことによって、現行の戦略や将来の戦略が抱える潜在的なリスクを評価し、事前に注視すべき指標や講じるべき対策を検討することが可能になります。
真に競争力のある組織とは、変化に迅速に対応できる組織です。シナリオプランニングは、未来の可能性を複数描き出し、それらを組織内で共有し、あたかも事前にリハーサルを行うかのように検討するプロセスを通じて、組織全体の柔軟性と変化への適応力を鍛え上げます。
完璧な予測を目指し、一度の決断ですべてを決定しようとするのではなく、複数のシナリオを通じて継続的に学習し、組織全体が賢くなっていくことこそが、「変化こそが定数」と言える現代において有効なアプローチです。シナリオは、日々発生する多様なシグナル(情報)を整理し、その意味を理解し、組織内で共有するための共通の枠組み、つまり「文脈」を提供します。これにより、日常の些細な兆候から、重大な変化が起こりつつあることを早期に察知できるようになるのです。
組織が実際に変化に対応していくためには、まずその構成員一人ひとりの頭の中、つまりものの見方を変えることが不可欠です。シナリオは、作成者の価値観から完全に独立することはできません。しかし、シナリオを作成する過程そのものが、自分たちがこれまでいかに既存の考え方の枠組み(マインド・セット)や事業環境の見方(メンタル・モデル)に縛られていたかを認識する契機となり、組織全体としての集団思考から脱却する助けとなるのです。
シナリオプランニングは、単なる未来予測の手法ではありません。それは、不確実な未来に主体的に向き合い、組織の思考様式、意思決定プロセス、そして行動様式そのものを変革し、持続的な競争優位を確立するための戦略的なアプローチなのです。
シナリオプランニングを導入しているグローバルな先進企業や公的団体の例をいくつかご紹介します。
先進企業 (グローバル):
- ロイヤル・ダッチ・シェル (Royal Dutch Shell): シナリオプランニングのパイオニアとして知られています。1970年代のオイルショックを契機に導入し、長期的な視点での戦略策定に活用してきました。
- BP (British Petroleum): エネルギー業界の変動に対応するため、複数の将来シナリオを描き、事業戦略に役立てています。
- INGグループ: 金融サービスにおける将来の不確実性に対応するため、シナリオプランニングをリスク管理や戦略策定に活用しています。
- BASF: 化学業界の長期的なトレンドや不確実性を分析し、シナリオプランニングを研究開発や事業ポートフォリオの検討に利用しています。
- 自動車業界の企業: 多くの自動車メーカーが、技術革新、市場の変化、規制の動向など、複雑な要因に対応するためにシナリオプランニングを導入しています。具体的な企業名は多岐にわたります。
- コンサルティングファーム: デロイト、PwC、アクセンチュアなどの大手コンサルティングファームは、自社の戦略策定だけでなく、クライアント企業へのシナリオプランニング導入支援も行っています。
公的団体 (グローバル):
- 国際エネルギー機関 (IEA): 世界のエネルギー需給に関する複数のシナリオを分析し、政策提言を行っています。
- 欧州環境庁 (EEA): 環境問題に関する将来のシナリオを提示し、政策決定の基礎となる情報を提供しています。
- 国連 (United Nations) の関連機関: 気候変動、人道支援、開発など、さまざまな分野で将来の可能性を探るためにシナリオプランニングの手法が用いられています。例えば、気候変動に関する政府間パネル (IPCC) は、地球温暖化の複数のシナリオを提示しています。
- 各国の政府機関: 国の長期的な政策やインフラ整備、安全保障などの分野において、シナリオプランニングを活用する事例が増えています。具体的な機関名は多岐にわたります。
これらの例は、シナリオプランニングが、業種やセクターを問わず、グローバルな規模で、将来の不確実性に対応し、より良い意思決定を行うための重要なツールとして認識されていることを示しています。
シナリオプランニングの事例
過去に公開したシナリオプランニングの事例(ケーススタディ)を以下にご紹介します。
事例一覧: https://qrk.co.jp/category/scenario-planning/
シナリオを活かした研究開発戦略の立案
上記事例で見てきたように、シナリオから得られた将来の社会、市場に対する洞察を研究開発戦略に活かすことが可能です。
シナリオを活かした研究開発戦略の立案:サプライチェーン再構築における国内化学メーカーの競争力維持
ここでは、サプライチェーン再構築という課題に対し、シナリオプランニングを活用した研究開発戦略の立案について解説します。こちらのケーススタディを引用しながら、以下の4つの項目に沿って議論を進めます。
- シナリオで描き出される社会、経済、法制度等の動きを把握する
- そのシナリオの世界では、どのような製品が用いられ、どのような技術が必要とされるかを分析する
- 現在の技術とのギャップを認識する
- 競合他社の動き、自社の技術的な強み、弱みから開発投資戦略を考える
1. シナリオで描き出される社会、経済、法制度等の動きを把握する
ケーススタディの4つのシナリオは、デジタル技術の進化と普及速度、そして新興国の台頭と製造技術の高度化という2つの重要な軸に基づき、2030年の社会、経済、法制度などの動きを描き出しています。
- シナリオA(共創の時代) では、デジタル技術が高度に浸透し、新興国との協調が進む社会が想定されます。経済はグローバルに連携し、技術標準化も進むと考えられます。法制度は、国際的な協調やオープンイノベーションを促進する方向へ進む可能性があります。
- シナリオB(停滞と衰退) では、デジタル技術の導入が遅れ、新興国に主導権を奪われる社会が描かれます。経済は地域分断が進み、保護主義的な政策が強まる可能性があります。法制度は、国内産業の保護を優先する方向へシフトするかもしれません。
- シナリオC(ニッチ戦略の成功) では、特定の分野でデジタル技術が活用され、新興国との距離を置く社会が想定されます。経済は多極化し、ニッチ市場における競争が激化するでしょう。法制度は、特定技術の保護や育成に重点が置かれる可能性があります。
- シナリオD(技術覇権の転換) では、新興国が技術革新を主導し、デジタル技術の導入が遅れた日本が取り残される社会が描かれます。経済は新興国中心となり、国際的な技術標準も新興国主導となる可能性があります。法制度は、技術革新を促進する新興国の動きに追随する形になるかもしれません。
これらのシナリオを分析することで、不確実な将来において、サプライチェーンや事業環境がどのように変化する可能性があるのか、その全体像を把握することができます。
2. そのシナリオの世界では、どのような製品が用いられ、どのような技術が必要とされるかを分析する
各シナリオで必要とされる製品と技術は大きく異なります。
- シナリオA では、効率的なグローバルサプライチェーンを支えるためのAI駆動型需要予測、ブロックチェーンによるトレーサビリティ、IoTによるリアルタイム管理技術、そしてオープンソースの化学シミュレーションツールなどが重要になります。製品としては、高度にカスタマイズされた高付加価値製品が求められるでしょう。
- シナリオB では、老朽化した国内プラントを維持するための省エネルギー技術や延命化技術、そして技術流出を防ぐためのサイバーセキュリティ技術が不可欠となります。製品は、価格競争に晒される汎用化学品が中心となる可能性があります。
- シナリオC では、高機能化学品の製造プロセス最適化技術、精密重合制御技術、特殊添加剤合成技術など、ニッチ市場で優位性を確立するための独自の技術が重要になります。製品は、特定の用途に特化した高機能製品が中心となるでしょう。
- シナリオD では、新興国が開発した革新的な化学プロセスや次世代触媒設計AI、データ駆動型プロセス開発技術などが求められます。日本国内では、一部の特殊高分子材料など、独自の技術を活かせる分野での製品開発に注力する必要があるかもしれません。
シナリオ別に必要となる製品と技術を具体的に分析することで、将来の市場ニーズや技術トレンドを予測し、研究開発の方向性を定めることができます。
3. 現在の技術とのギャップを認識する
上記の分析を踏まえ、自社の現在の技術力と比較することで、各シナリオに対応するために克服すべきギャップを認識します。
例えば、シナリオA を重視する場合、自社のAI・IoT技術のレベル、グローバルサプライチェーン管理能力、新興国企業との連携経験などを評価し、不足している点を明確にする必要があります。シナリオD を意識するのであれば、新興国の技術革新のスピードや研究開発の方向性を把握し、自社の技術開発体制や投資戦略を見直す必要が出てくるでしょう。
シナリオ別の技術開発リストは、具体的なギャップを認識する上で非常に有用です。リストアップされた技術要素ごとに、自社の現状レベル、開発状況、競争優位性などを評価することで、優先的に取り組むべき技術領域を特定できます。
4. 競合他社の動き、自社の技術的な強み、弱みから開発投資戦略を考える
最後に、各シナリオにおける競合他社の動きを予測し、自社の技術的な強みと弱みを考慮しながら、最適な開発投資戦略を策定します。主な戦略としては、以下のものが挙げられます。
- ヘッジ戦略: どのシナリオが現実化しても、一定のリターンが得られるような技術開発に着手する戦略です。例えば、省エネルギー技術や環境負荷低減技術などは、多くのシナリオで共通して重要となる可能性があり、リスクを分散する意味で有効な投資対象となります。
- ギャンブル戦略: 可能性が最も高いと思われる特定のシナリオを一つ選び、そのシナリオで重要となる技術開発に全リソースを投入する戦略です。この戦略は、成功した場合に大きなリターンが期待できる反面、シナリオが外れた場合には大きな損失を被るリスクがあります。
- 留保戦略: 現状が極めて不確実性が高く、仮に投資を留保しても、後から十分キャッチアップできると判断される場合に取る戦略です。この戦略は、初期投資を抑えることができますが、競合他社に先手を打たれるリスクや、技術トレンドの変化に対応しきれなくなる可能性があります。
- オプション戦略: 最も可能性の高いシナリオに初期投資を行いながらも、外部環境の変化に応じて柔軟に戦略を切り替えることができるよう、複数の技術開発の可能性を残しておく戦略です。これにより、リスクを最小限に抑えつつ、将来の成長機会を最大限に活かすことが可能になります。
ケーススタディでは、オプション戦略が最も有効であると結論付けられました。これは、不確実性の高い状況下では、将来の複数の可能性に対応できるよう、柔軟な投資を行うことが重要であるためです。
シナリオA(共創の時代) を最有力と見なし、AI駆動型需要予測モデルの高度化に優先的に投資しつつ、他のシナリオの可能性も視野に入れた研究開発を進めることが推奨されます。
自社の強み、例えば高度な材料設計技術や精密な製造プロセス技術などを活かしながら、弱点であるデジタル技術の導入や新興国との連携を強化する方向で投資を行うことが考えられます。また、競合他社がどのような技術に注力しているのかを分析し、自社が優位性を確立できる領域を見極めることも重要です。
例えば、富士フイルムのケーススタディのように、特定の成長市場(インドの半導体産業)に早期に進出し、サプライチェーンの再構築に対応する動きは、シナリオA を見据えたオプション戦略の一環と言えるでしょう。
今回あらためて、シナリオプランニングとは何か?について、記事にしてみました。 クォークでは、生成AIを活用した客観性のある戦略プランニング、特定分野に専門特化した生成AIの構築など、企業のR&Dを情報面でサポートする取り組みを継続しております。全国からのお問い合わせをお待ちしております。